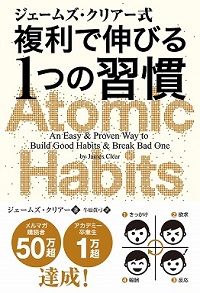筆者が後で見返すためのまとめ
最近、時間を消費しない音のコンテンツにはまっています。作業しながら耳で本を読む Audible もおすすめです。
久しぶりにキーボードを打ちながら読みたくなる良い本でした。
この記事は、筆者自身が後で見返すためにまとめているものです。
書籍の内容をざっくり
より後から見返したいものを上にしています。
習慣のコツ
習慣に関する検討をするときに確認するチートシート。
良い習慣の身に付け方
| 1 | はっきりさせる | |
|---|---|---|
| 1-1 | 習慣得点表をつける | 現在の習慣に気づく |
| 1-2 | 実行意図を使う | いつ、どこで、何をする |
| 1-3 | 習慣の積み上げ | 現在の習慣 → 新しい習慣 |
| 1-4 | 環境をつくる | きっかけのはっきり見える化 |
| 2 | 魅力的にする | |
|---|---|---|
| 2-1 | 魅力の抱き合わせ | 〝したい〟と〝するべき〟をセットに |
| 2-2 | 環境を変える | それが当たり前の環境に身を置く |
| 2-3 | ルーチン | モチベーションを高める儀式 |
| 3 | 易しくする | |
|---|---|---|
| 3-1 | 抵抗を減らす | 良い習慣へのステップを減らす |
| 3-2 | 環境を準備 | 未来の行動がとりやすくなる環境 |
| 3-3 | 決定の瞬間 | 大きな影響をもたらす小さな選択をする |
| 3-4 | 2分間ルール | 習慣を2分でできるものに縮小する |
| 3-5 | 自動化 | テクノロジーや設備の導入 |
| 4 | 満足できるものにする | |
|---|---|---|
| 4-1 | 強化を利用 | 習慣の完了後、すぐに報酬を与える |
| 4-2 | 何もしないを楽しく | 悪い習慣を避けるときに利益が見えるように |
| 4-3 | 習慣トラッカー | 習慣の連続を記録し、連鎖が切れないように |
| 4-4 | 2回さぼらない | 習慣を忘れたらすぐに元に戻す |
悪い習慣の止め方
| 1 | はっきりさせる | |
|---|---|---|
| 1-5 | 避ける | きっかけを環境から取り除く |
| 2 | 魅力的にする | |
|---|---|---|
| 2-4 | 考え方を変える | 悪い習慣をやめて得る利益を強調する |
| 3 | 易しくする | |
|---|---|---|
| 3-6 | 抵抗を増やす | 悪い習慣へのステップを増やす |
| 3-7 | 背水の陣法 | 未来の選択が役立つようになるよう制限をかける |
| 4 | 満足できるものにする | |
|---|---|---|
| 4-5 | パートナー | 誰かに見張ってもらう |
| 4-6 | 習慣契約書 | 悪い習慣 → 人に知られて苦痛を感じるように |
補足
習慣得点表
- 日本の鉄道の指差喚呼がモデル
- 毎日の習慣をリストアップして、良い(+)悪い(-)どちらでもない(=)の印をつけていく
習慣の積み上げ
- ディドロ効果――ひとつの購入がさらなる購入を呼ぶ傾向
- 現在の習慣、毎日必ず起こることをリストアップして、適切な習慣を結びつける
- きっかけが具体的で、すぐ実行できるときが、最も上手くいく
環境をつくる
- モチベーションを過大評価せず、環境を重視する
- 良い習慣のきっかけを、目立たせ、近づける。悪い習慣のきっかけを遠ざける
- きっかけが同居していると、欲求の強い方が採用されてしまう
魅力的にする
- 習慣はドーパミン主導のフィードバックループ
- コカイン中毒者は、コカインを摂取したあとではなく粉を見たときにドーパミンが出る
- 人間を動かすのは、報酬の現実ではなく、報酬の予測――したい行動とするべき行動をセットにするとモチベーションが上がるという理屈
- 習慣になりやすい商品は潜在動機をうまくつかんでいる――エネルギーを節約する、食物と水を手に入れる、恋人をみつけて子どもをつくる、他人とつながり絆を深める、社会的に承認される、不安を解消する、地位や名声を獲得する
満足できるものにする
- 報われる行動は繰り返す。罰せられる行動は避ける
- 即時報酬と遅延報酬のずれ――野生は即時報酬の環境、現代社会は遅延報酬の環境
- 時間割引、双曲割引(行動経済学)――脳による報酬の評価は、時間と相反する。人は未来よりも現在を高く評価する
- 回避の習慣を身につけようとする際に役立つ――禁煙、禁酒
習慣トラッカー
- 7つの習慣
なぜ小さな変化が大きな違いをもたらすのか
習慣には四つのステップがあり、著者のそれは「オペラント条件づけ」を取り入れた認知科学と行動科学の統合モデルである。
- オペラント条件づけ――外からの刺激が習慣に与える影響
- 幸せの3条件
- 自己受容――自分で自分を認めている状態
- 他者信頼――他者を信じられている状態
- 貢献感――自分が役に立っている感覚
最小習慣の驚くべき力
小さな習慣が大きな変化をもたらす理由
投資における複利運用は人間の習慣にも当てはまる。そして、複利運用と同様に習慣は諸刃の剣である。(良い習慣と悪い習慣)
進歩とはどういうものか
- 閾値や臨界点のようなものがある
- 潜在能力のプラトー(停滞期間)
- 社会改革主義者ジェイコブ・リース
何をやっても無駄に思えるとき、わたしは石工がハンマーで岩を叩き割るのを見にいく。おそらく100回叩いても、岩にはひびひとつ見られない。ところが101回目に叩いたとき、岩はふたつに割れる。岩を割ったのは最後の一打ちではない。それまでのすべての殴打である。 目標を忘れて、仕組みに集中しよう
目標は達成したい結果、仕組みは結果へと導くプロセス
結果は仕組みに左右される目標には方向を定める効果がある。仕組みは進歩するのに最適である。目標について考えるのに時間を費やしすぎて、仕組みを考える時間がないと、いくつかの問題が生じてくる。
- 勝者も敗者も目標は同じ――すべてのオリンピック選手は金メダルを目標としている
- 目標達成は一時的な変化にすぎない
- 目標は幸福を制限する
- 目標は長期的な進歩と相容れない
習慣がアイデンティティーを形成する(逆もまた真なり)
習慣を変えるのが難しい理由
- 変えようとするものが間違っている
- 習慣を変えるための方法が間違っている
行動変化の3つの層
結果ベースの習慣(1を達成、次に2を達成、最後に3を達成)は続きづらい、どのような人になりたいかというアイデンティティベースの習慣(3があり、2と1を得る)を身につけると良い。習慣はアイデンティティーを体現する方法。
- 結果の変化
- プロセスの変化
- アイデンティティーの変化
禁煙者がたばこを断るときに、
- 「やめようとしているので」→ 喫煙者と認識して、違う結果を求めている
- 「わたしはたばこを吸いませんので」→ アイデンティティの変化を表す
人となりを変える最も効果的な方法は行動を変えること
1ページ書く度に作家になり、バイオリンを練習する度に音楽家になり、トレーニングをはじめる度にアスリートになり、従業員を励ますたびにリーダーになる。
アイデンティティーを変えるための二段階のプロセス
- どのようなタイプの人になりたいかを決める
- 小さな勝利で自分自身に証明する
シンプルな四つのステップで良い習慣を身につける
心理学者エドワード・ソーンダイクによるネコの実験
- 満足できる結果につながる行動は繰り返されやすい
- 不快な結果を生む行動は繰り返されにくい
フィードバックループ
「試行、失敗、学習、別の方法で試行」というループ。
習慣は認知的負荷を減らす
習慣が作られると、脳の活動レベルが下がっていく。つまり、人生の問題をできるだけ少ないエネルギーと努力で解決することができるようになる。
習慣の働き方の科学
習慣形成のプロセスは、「きっかけ、欲求、反応、報酬」の四つ。四つのステップのどれかが欠けると習慣にならない。
- きっかけ――金や名声、権力や地位、賞賛や承認、恋や友情、個人的な満足感(間接的に生き残りや繁殖がしやすくなる → 全行動の背後にある深い動機)
- 欲求――たばこを吸うことを求めているのではなく、たばこによって気持ちが落ち着くことを望んでいる(どの欲求も心の状態を変えたいという願望とつながっている)
- 反応――どれだけやる気になっているか、行動に抵抗を感じるか、能力にもよる
- 報酬――あらゆる習慣の最終目標。報酬に気づき(きっかけ)、報酬を欲しがり(欲求)、報酬を獲得する(行動)。報酬は、ふたつの目的を満たす。1.満足 2.学習
書籍を読んで
この記事には、筆者が次の習慣を考えるときに必要な情報をまとめたので、根拠の箇所をがっつり削っている。根拠が気になる方は書籍を読むのが良いと思う。
最近、時間を消費しない音のコンテンツにはまっています。作業しながら耳で本を読む Audible もおすすめです。
先手必勝
目標について考えるのに時間を費やしすぎて、仕組みを考える時間がないと、いくつかの問題が生じてくる。
過去の営業時代を思い出した。盲目的に仕事をするのは本当に性に合わない。
即時報酬と遅延報酬のずれは投資にも当てはまる
即時報酬と遅延報酬のずれ――野生は即時報酬の環境、現代社会は遅延報酬の環境
勝てない投資家は、即時報酬を求めているように思う。
習慣 ≒ プログラミング
- 投資における複利運用は人間の習慣にも当てはまる。そして、複利運用と同様に習慣は諸刃の剣である。(良い習慣と悪い習慣)
- 習慣が作られると、脳の活動レベルが下がっていく――習慣は認知的負荷を減らす
すごく合点がいった。また、習慣を構築していく様子は、プログラミングをしていくのに良く似ていると感じた。
| 習慣 | プログラミング | |
|---|---|---|
| 1.脳のクセがある | 1.プログラミング言語ごとの仕様がある | |
| 2.クセに合わせて習慣をつくる | 2.機能を組み合わせてプログラムする | |
| 3.少ないリソースで同じことができるようになる | 3.特定の処理を自動化することができる | |
| 4.他の活動に脳のリソースを当てる | 4.他の活動に時間を割ける |
習慣が作られると、少ない脳のリソースで同じことができる。その分、他の活動にリソースを当てることができる。つまり、習慣は時間をかけて行う〝脳の自動化〟と言えそう。生活に取り入れたいことをリストアップしておいて、時間をかけて脳に覚えさせる(習慣化する)。
そう考えると面白い。
筆者の土俵
自分の土俵はやっぱり〝ものをつくる〟だと思う。一流の営業マンのように大きなお金を集めたり動かしたりは性に合わない。人並み(ある意味、人並み以上)にできるようになる必要はあると思うけど、やっていて楽しいのは〝ものづくり〟と断言できる。
- ものをづくり(プログラムや習慣を含む)で価値を生む
- 価値をストックする
- 複利を生む
抽象化すると、こんな感じだと思う。
習慣のコツ
すでに取り入れていることも結構あった。
- 習慣の積み上げ
- 帰宅ラン
- 出社したらトレーニングとストレッチをする
- 習慣トラッカー
- Googleカレンダーで管理
筆者にとっては、断片的に色々なところにあった情報が、
- 明確な根拠が添えられて
- 体系的にまとめられている
という印象。

タカハシ ユウヤ
投資やプログラミング、動画コンテンツの撮影・制作・編集などが得意。元・日本料理の板前。更新のお知らせは、Twitterで。
- 記事をシェア